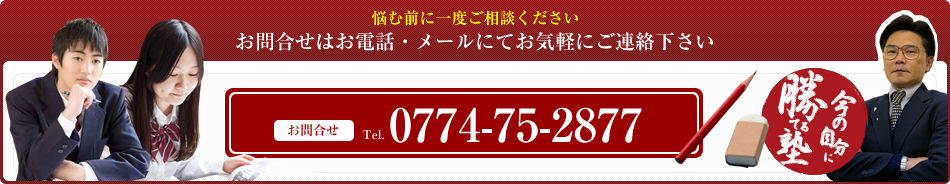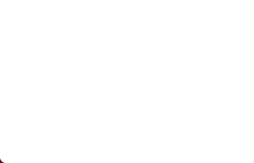立松和平の「海の命」が教材として教科書などで取り上げられているのを見かける。
教材として取り上げられる訳なので、ここから何か学び取らなければいけないのだろう。
父親の顔も知らない太一が父親を超える村一番の漁師を目指して成長していく様子が描かれている。父親が海で死んだときはそのもりが瀬の主と思われるクエに刺さっていたという。太一は、父の命を奪ったと思われる瀬の主を殺せば父親を超えると思っている。そして、クライマックスで、太一は瀬の主と思われるクエを目の前にする。そして、太一はクエを殺すことを思いとどまる。
ある授業で、先生が子供達に「どうして、太一はクエを殺さなかったのだろう」と問いかけた。
子供達はいろいろな答えを導き出した。先生は「瀬の主を殺して海が死ねば、漁師である太一も死んでしまうと思うようになったから」という答えを用意していたようだが、「クエが父親だと思ったから」という、答えが子供達から複数出てきた。たしかに、本文にはそのようなことが書かれている。
しかし、先生がある学びを目的として指導をするなら、そうした、先生の意図と異なる答えに生徒を導いたのでは、やはり、授業が成功とはいえない。文学作品を教材とするときに、その作品そのものを学ぶだけではいけない。この作品を通して、その他のいろいろな文学作品を読むのに必要な知識や考え方を学ばなければいけない。教師はその作品固有の表現方法と文章の構造を子供達に詳細に教える。しかし、それだけでは、子供達は他の作品を読むときにどうすればいいのか分かるようにはならないのだ。
ここでは、太一の成長が描かれているのだから、表現の変化に注目していくようにする。その変化が主人公の成長と重なるということに気づかせてあげるようにした方が、他の文学作品を読むときにも応用が利くだろう。そして、私たちは、子供達をそこへ連れて行くように、自分自身の授業を見つめ直すのだ。